去る者は日日に疎しとは
去る者は日日に疎し
さるものはひびにうとし
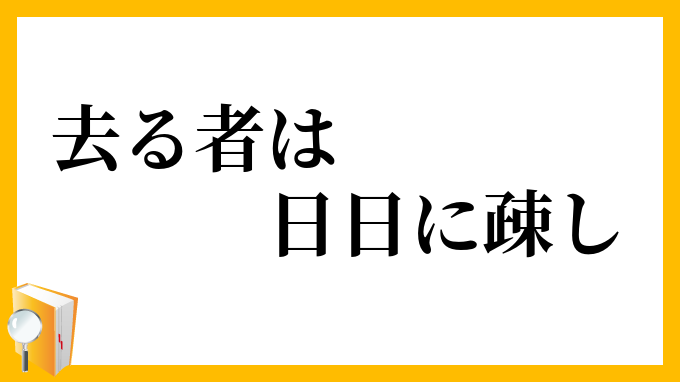
| 言葉 | 去る者は日日に疎し |
|---|---|
| 読み方 | さるものはひびにうとし |
| 意味 | 死んだ人は、月日が経つとだんだんと忘れられていく。また、親しくしていた人も、遠く離れてしまうとしだいに疎遠になるということ。 |
| 異形 | 去る者は日々に疎し(さるものはひびにうとし) |
| 類句 | 遠くなれば薄くなる(とおくなればうすくなる) |
| 使用語彙 | 去る |
| 使用漢字 | 去 / 者 / 日 / 疎 / 々 |
「去」を含むことわざ
- 一難去ってまた一難(いちなんさってまたいちなん)
- 華を去り実に就く(かをさりじつにつく)
- 帰去来(ききょらい)
- 去り跡へ行くとも死に跡へ行くな(さりあとへゆくともしにあとへゆくな)
- 去る者は追わず(さるものはおわず)
- 去る者は追わず、来る者は拒まず(さるものはおわず、きたるものはこばまず)
- 七尺去って師の影を踏まず(しちしゃくさってしのかげをふまず)
- 弟子七尺去って師の影を踏まず(でししちしゃくさってしのかげをふまず)
「者」を含むことわざ
- 愛出ずる者は愛返り、福往く者は福来る(あいいずるものはあいかえり、ふくゆくものはふくきたる)
- 青表紙を叩いた者にはかなわぬ(あおびょうしをたたいたものにはかなわぬ)
- 赤子のうちは七国七里の者に似る(あかごのうちはななくにななさとのものににる)
- 垢で死んだ者はない(あかでしんだものはない)
- 当たった者のふの悪さ(あたったもののふのわるさ)
- 新たに沐する者は必ず冠を弾く(あらたにもくするものはかならずかんむりをはじく)
- 医者が取るか坊主が取るか(いしゃがとるかぼうずがとるか)
- 医者寒からず儒者寒し(いしゃさむからずじゅしゃさむし)
- 医者上手にかかり下手(いしゃじょうずにかかりべた)
- 医者と味噌は古いほどよい(いしゃとみそはふるいほどよい)
「日」を含むことわざ
- 秋風と夫婦喧嘩は日が入りゃ止む(あきかぜとふうふげんかはひがいりゃやむ)
- 秋の入り日と年寄りはだんだん落ち目が早くなる(あきのいりひととしよりはだんだんおちめがはやくなる)
- 秋の日と娘の子はくれぬようでくれる(あきのひとむすめのこはくれぬようでくれる)
- 秋の日は釣瓶落とし(あきのひはつるべおとし)
- 秋日和半作(あきびよりはんさく)
- 明後日の方(あさってのほう)
- 朝日が西から出る(あさひがにしからでる)
- 明日は明日の風が吹く(あしたはあしたのかぜがふく)
- 明日ありと思う心の仇桜(あすありとおもうこころのあだざくら)
- 明日食う塩辛に今日から水を飲む(あすくうしおからにきょうからみずをのむ)
「疎」を含むことわざ
- 悪女は鏡を疎む(あくじょはかがみをうとむ)
- 徒疎か(あだおろそか)
- あだや疎か(あだやおろそか)
- 徒や疎か(あだやおろそか)
- 世事に疎い(せじにうとい)
- 天網恢々疎にして漏らさず(てんもうかいかいそにしてもらさず)
- 天網恢恢疎にして漏らさず(てんもうかいかいそにしてもらさず)



