大事は小事より起こるとは
大事は小事より起こる
だいじはしょうじよりおこる
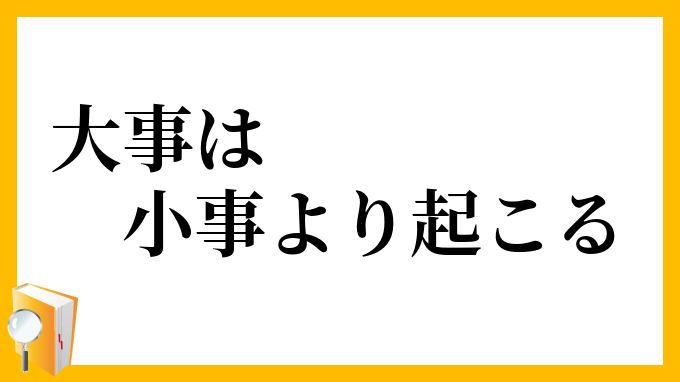
| 言葉 | 大事は小事より起こる |
|---|---|
| 読み方 | だいじはしょうじよりおこる |
| 意味 | どのような大事も、取るに足りない小さなことが原因となって引き起こされるということ。小さな油断にも気をつけよという戒めの言葉。 |
| 使用語彙 | 小事 / より / 起こる |
| 使用漢字 | 大 / 事 / 小 / 起 |
「大」を含むことわざ
- 諍いをしいしい腹を大きくし(いさかいをしいしいはらをおおきくし)
- 井の中の蛙大海を知らず(いのなかのかわずたいかいをしらず)
- 上を下への大騒ぎ(うえをしたへのおおさわぎ)
- 独活の大木(うどのたいぼく)
- 瓜の皮は大名に剝かせよ、柿の皮は乞食に剝かせよ(うりのかわはだいみょうにむかせよ、かきのかわはこじきにむかせよ)
- 江戸っ子の往き大名還り乞食(えどっこのゆきだいみょうかえりこじき)
- 江戸は八百八町、大坂は八百八橋(えどははっぴゃくやちょう、おおさかははっぴゃくやばし)
- お家の一大事(おいえのいちだいじ)
- 大当たりを取る(おおあたりをとる)
- 大嘘はつくとも小嘘はつくな(おおうそはつくともこうそはつくな)
「事」を含むことわざ
- 秋葉山から火事(あきばさんからかじ)
- 悪事千里を走る(あくじせんりをはしる)
- 悪事身に返る(あくじみにかえる)
- 悪は一旦の事なり(あくはいったんのことなり)
- 明日の事は明日案じよ(あすのことはあすあんじよ)
- 明日の事を言えば鬼が笑う(あすのことをいえばおにがわらう)
- 当て事と越中褌は向こうから外れる(あてごととえっちゅうふんどしはむこうからはずれる)
- 言うに事欠いて(いうにことかいて)
- 一事が万事(いちじがばんじ)
- 色よい返事(いろよいへんじ)
「小」を含むことわざ
- 愛想も小想も尽き果てる(あいそもこそもつきはてる)
- 愛は小出しにせよ(あいはこだしにせよ)
- 戴く物は夏も小袖(いただくものはなつもこそで)
- 因果の小車(いんがのおぐるま)
- 旨い物は小人数(うまいものはこにんずう)
- 大嘘はつくとも小嘘はつくな(おおうそはつくともこうそはつくな)
- 大木の下に小木育たず(おおきのしたにおぎそだたず)
- 大木の下に小木育つ(おおきのしたにおぎそだつ)
- 大遣いより小遣い(おおづかいよりこづかい)
- 大摑みより小摑み(おおづかみよりこづかみ)



