預言者郷里に容れられずとは
預言者郷里に容れられず
よげんしゃきょうりにいれられず
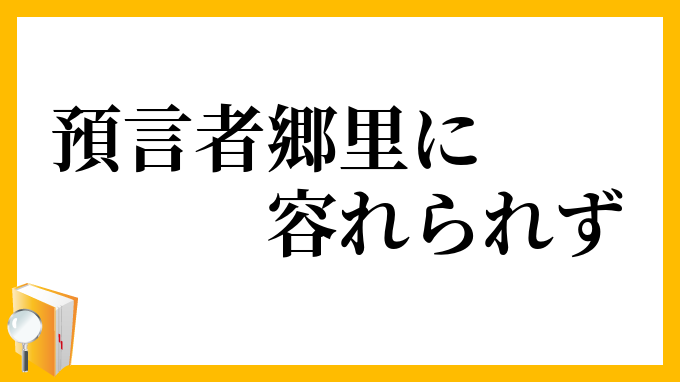
| 言葉 | 預言者郷里に容れられず |
|---|---|
| 読み方 | よげんしゃきょうりにいれられず |
| 意味 | 優れた人物であっても、身近な人には認められず尊敬されにくいということ。
すぐれた預言者も、子どもの頃からよく知っている人たちにとっては、普通の人しか思えないため尊ばれないとの意から。 |
| 出典 | 『新約聖書』 |
| 使用語彙 | 預言 |
| 使用漢字 | 預 / 言 / 者 / 郷 / 里 / 容 |
「預」を含むことわざ
- 預かり物は半分の主(あずかりものははんぶんのぬし)
- 命を預かる(いのちをあずかる)
- 命を預ける(いのちをあずける)
- お預けを食う(おあずけをくう)
- 下駄を預ける(げたをあずける)
- 台所を預かる(だいどころをあずかる)
- 盗人に鍵を預ける(ぬすびとにかぎをあずける)
「言」を含むことわざ
- ああ言えばこう言う(ああいえばこういう)
- 合言葉にする(あいことばにする)
- 呆れて物が言えない(あきれてものがいえない)
- 明日の事を言えば鬼が笑う(あすのことをいえばおにがわらう)
- あっと言う間(あっというま)
- あっと言わせる(あっといわせる)
- 後から剝げる正月言葉(あとからはげるしょうがつことば)
- 穴を掘って言い入れる(あなをほっていいいれる)
- 有り体に言う(ありていにいう)
- 言い得て妙(いいえてみょう)
「者」を含むことわざ
- 愛出ずる者は愛返り、福往く者は福来る(あいいずるものはあいかえり、ふくゆくものはふくきたる)
- 青表紙を叩いた者にはかなわぬ(あおびょうしをたたいたものにはかなわぬ)
- 赤子のうちは七国七里の者に似る(あかごのうちはななくにななさとのものににる)
- 垢で死んだ者はない(あかでしんだものはない)
- 悪女の賢者ぶり(あくじょのけんじゃぶり)
- 当たった者のふの悪さ(あたったもののふのわるさ)
- 新たに沐する者は必ず冠を弾く(あらたにもくするものはかならずかんむりをはじく)
- 医者が取るか坊主が取るか(いしゃがとるかぼうずがとるか)
- 医者寒からず儒者寒し(いしゃさむからずじゅしゃさむし)
- 医者上手にかかり下手(いしゃじょうずにかかりべた)
「郷」を含むことわざ
- 故郷へ錦を飾る(こきょうへにしきをかざる)
- 故郷忘じ難し(こきょうぼうじがたし)
- 郷に入っては郷に従え(ごうにいってはごうにしたがえ)
- 妻子を置く所が故郷(さいしをおくところがこきょう)
- 桃源郷(とうげんきょう)
- 無何有の郷(むかうのさと)
「里」を含むことわざ
- 赤子のうちは七国七里の者に似る(あかごのうちはななくにななさとのものににる)
- 悪事千里を走る(あくじせんりをはしる)
- 朝茶は七里帰っても飲め(あさちゃはしちりかえってものめ)
- 牛も千里馬も千里(うしもせんりうまもせんり)
- 縁あれば千里(えんあればせんり)
- お里が知れる(おさとがしれる)
- 門松は冥土の旅の一里塚(かどまつはめいどのたびのいちりづか)
- 好事門を出でず、悪事千里を行く(こうじもんをいでず、あくじせんりをいく)
- 酒屋へ三里、豆腐屋へ二里(さかやへさんり、とうふやへにり)
- 囁き千里(ささやきせんり)



