鳴く猫は鼠を捕らぬとは
鳴く猫は鼠を捕らぬ
なくねこはねずみをとらぬ
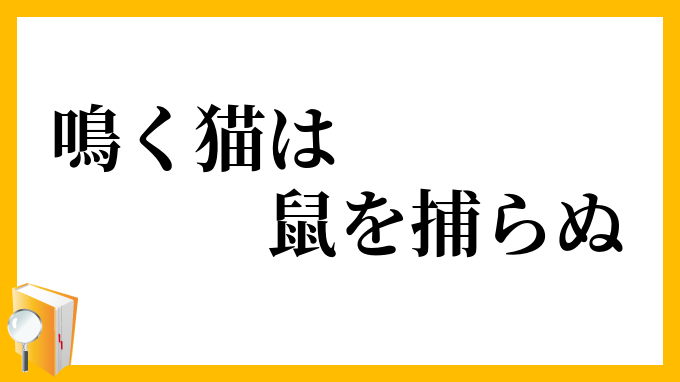
| 言葉 | 鳴く猫は鼠を捕らぬ |
|---|---|
| 読み方 | なくねこはねずみをとらぬ |
| 意味 | 口数が多い者は、とかく口先だけで実行が伴わないというたとえ。よく鳴く猫は鼠を捕らないということから。 |
| 類句 | 吠える犬はめったに噛みつかない(ほえるいぬはめったにかみつかない) |
| 使用語彙 | 鳴く / 鼠 |
| 使用漢字 | 鳴 / 猫 / 鼠 / 捕 |
「鳴」を含むことわざ
- 雨塊を破らず、風枝を鳴らさず(あめつちくれをやぶらず、かぜえだをならさず)
- 今鳴いた烏がもう笑う(いまないたからすがもうわらう)
- 鶯鳴かせたこともある(うぐいすなかせたこともある)
- 打たねば鳴らぬ(うたねばならぬ)
- 腕が鳴る(うでがなる)
- 腕を鳴らす(うでをならす)
- 嬉しい悲鳴(うれしいひめい)
- 枝を鳴らさず(えだをならさず)
- 蚊の鳴くような声(かのなくようなこえ)
- 烏の鳴かない日はあっても(からすのなかないひはあっても)
「猫」を含むことわざ
- 秋の雨が降れば猫の顔が三尺になる(あきのあめがふればねこのかおがさんじゃくになる)
- 犬は人につき猫は家につく(いぬはひとにつきねこはいえにつく)
- 男猫が子を生む(おとこねこがこをうむ)
- 女の心は猫の目(おんなのこころはねこのめ)
- 借りてきた猫(かりてきたねこ)
- 窮鼠、猫を噛む(きゅうそ、ねこをかむ)
- 結構毛だらけ猫灰だらけ(けっこうけだらけねこはいだらけ)
- 皿嘗めた猫が科を負う(さらなめたねこがとがをおう)
- 上手の猫が爪を隠す(じょうずのねこがつめをかくす)
- たくらだ猫の隣歩き(たくらだねこのとなりあるき)
「鼠」を含むことわざ
- 頭の黒い鼠(あたまのくろいねずみ)
- 家に鼠、国に盗人(いえにねずみ、くににぬすびと)
- 窮鼠、猫を噛む(きゅうそ、ねこをかむ)
- 国に盗人、家に鼠(くににぬすびと、いえにねずみ)
- 独楽鼠のよう(こまねずみのよう)
- 大山鳴動して鼠一匹(たいざんめいどうしてねずみいっぴき)
- 泰山鳴動して鼠一匹(たいざんめいどうしてねずみいっぴき)
- ただの鼠ではない(ただのねずみではない)
- 黙り猫が鼠を捕る(だまりねこがねずみをとる)
- 時に遇えば鼠も虎になる(ときにあえばねずみもとらになる)



