案じるより団子汁とは
案じるより団子汁
あんじるよりだんごじる
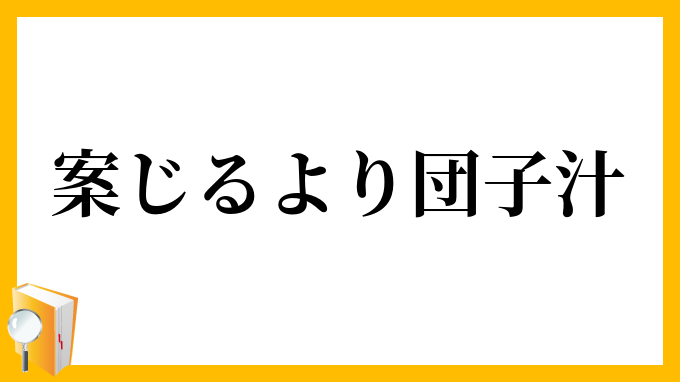
| 言葉 | 案じるより団子汁 |
|---|---|
| 読み方 | あんじるよりだんごじる |
| 意味 | あれこれ心配しても仕方ないから、団子汁でも食べて気を紛らわしたほうがよいという助言。
「案じる」は「餡汁」の語呂合わせ。 団子汁は餡汁に団子を入れたもの。ただの餡汁よりいいというしゃれでもある。 |
| 使用語彙 | 案じる / より |
| 使用漢字 | 案 / 団 / 子 / 汁 |
「案」を含むことわざ
- 明日の事は明日案じよ(あすのことはあすあんじよ)
- 頭の濡れぬ思案(あたまのぬれぬしあん)
- 案じてたもるより銭たもれ(あんじてたもるよりぜにたもれ)
- 案ずるより産むが易し(あんずるよりうむがやすし)
- 案に相違する(あんにそういする)
- 案に違う(あんにたがう)
- 一計を案じる(いっけいをあんじる)
- 色は思案の外(いろはしあんのほか)
- 鎹思案(かすがいじあん)
「団」を含むことわざ
- 石亀の地団駄(いしがめのじだんだ)
- 石亀も地団駄(いしがめもじだんだ)
- 石に布団は着せられず(いしにふとんはきせられず)
- 蛙が飛べば石亀も地団駄(かえるがとべばいしがめもじだんだ)
- 雁が飛べば石亀も地団駄(がんがとべばいしがめもじだんだ)
- 地団太を踏む(じだんだをふむ)
- 鷹が飛べば石亀も地団駄(たかがとべばいしがめもじだんだ)
- 炭団に目鼻(たどんにめはな)
- 団結は力なり(だんけつはちからなり)
「子」を含むことわざ
- 赤子のうちは七国七里の者に似る(あかごのうちはななくにななさとのものににる)
- 赤子の腕を捩じる(あかごのうでをねじる)
- 赤子の手をねじる(あかごのてをねじる)
- 赤子の手を捩じるよう(あかごのてをねじるよう)
- 赤子の手を捻る(あかごのてをひねる)
- 赤子の手を捻るよう(あかごのてをひねるよう)
- 赤子は泣き泣き育つ(あかごはなきなきそだつ)
- 赤子を裸にしたよう(あかごをはだかにしたよう)
- 秋茄子は嫁に食わすな(あきなすはよめにくわすな)
- 秋の日と娘の子はくれぬようでくれる(あきのひとむすめのこはくれぬようでくれる)



