勝負は時の運とは
勝負は時の運
しょうぶはときのうん
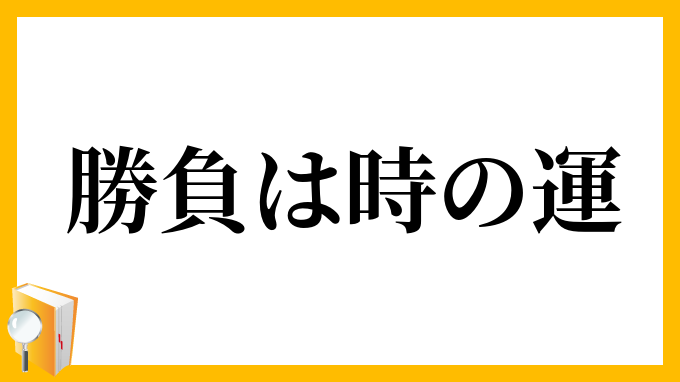
| 言葉 | 勝負は時の運 |
|---|---|
| 読み方 | しょうぶはときのうん |
| 意味 | 勝負はその時々の運によるもので、必ずしも実力通りに決まるものではないということ。
「勝負は時のはずみ」「勝つも負けるも時の運」「勝つも負けるも運次第」「負けるも勝つも時の運」「負けるも勝つも運次第」などともいう。 |
| 異形 | 勝負は時のはずみ(しょうぶはときのはずみ) |
| 勝つも負けるも時の運(かつもまけるもときのうん) | |
| 勝つも負けるも運次第(かつもまけるもうんしだい) | |
| 負けるも勝つも時の運(まけるもかつもときのうん) | |
| 負けるも勝つも運次第(まけるもかつもうんしだい) | |
| 使用語彙 | 勝負 / 勝つ |
| 使用漢字 | 勝 / 負 / 時 / 運 / 次 / 第 |
「勝」を含むことわざ
- あるはないに勝る(あるはないにまさる)
- 言い勝ち功名(いいがちこうみょう)
- 生きている犬は死んだライオンに勝る(いきているいぬはしんだらいおんにまさる)
- 言わぬは言うに勝る(いわぬはいうにまさる)
- 得手勝手は向こうには効かない(えてかってはむこうにはきかない)
- 男勝り(おとこまさり)
- 買うは貰うに勝る(かうはもらうにまさる)
- 勝ち鬨を挙げる(かちどきをあげる)
- 勝ち名乗りを上げる(かちなのりをあげる)
- 勝ちに乗ずる(かちにじょうずる)
「負」を含むことわざ
- 負うた子に教えられて浅瀬を渡る(おうたこにおしえられてあさせをわたる)
- 負うた子より抱いた子(おうたこよりだいたこ)
- 負うた子を三年探す(おうたこをさんねんさがす)
- 負ぶえば抱かりょう(おぶえばだかりょう)
- 負わず借らずに子三人(おわずからずにこさんにん)
- 勝った自慢は負けての後悔(かったじまんはまけてのこうかい)
- 勝てば官軍、負ければ賊軍(かてばかんぐん、まければぞくぐん)
- 鴨が葱を背負って来る(かもがねぎをしょってくる)
- 堪忍五両、負けて三両(かんにんごりょう、まけてさんりょう)
- 笈を負う(きゅうをおう)
「時」を含むことわざ
- 挨拶は時の氏神(あいさつはときのうじがみ)
- 朝顔の花一時(あさがおのはなひととき)
- 朝の一時は晩の二時に当たる(あさのひとときはばんのふたときにあたる)
- あの声で蜥蜴食らうか時鳥(あのこえでとかげくらうかほととぎす)
- ある時は米の飯(あるときはこめのめし)
- ある時払いの催促なし(あるときばらいのさいそくなし)
- いざという時(いざというとき)
- 何時にない(いつにない)
- 今を時めく(いまをときめく)
- 飢えたる時は食を択ばず(うえたるときはしょくをえらばず)
「運」を含むことわざ
- 足を運ぶ(あしをはこぶ)
- 運が開ける(うんがひらける)
- 運が向く(うんがむく)
- 運根鈍(うんこんどん)
- 運は天にあり(うんはてんにあり)
- 運は寝て待て(うんはねてまて)
- 運用の妙は一心に存す(うんようのみょうはいっしんにそんす)
- 運を天に任せる(うんをてんにまかせる)
- 運を待つは死を待つに等し(うんをまつはしをまつにひとし)
- 川に水運ぶ(かわにみずはこぶ)
「次」を含むことわざ
- 阿弥陀の光も銭次第(あみだのひかりもぜにしだい)
- 蹴る馬も乗り手次第(けるうまものりてしだい)
- 事と次第によっては(こととしだいによっては)
- 娑婆で見た弥次郎(しゃばでみたやじろう)
- 地獄の沙汰も金次第(じごくのさたもかねしだい)
- 次郎にも太郎にも足りぬ(じろうにもたろうにもたりぬ)
- 成るも成らぬも金次第(なるもならぬもかねしだい)
- 二の次にする(にのつぎにする)
- 恥と頭は搔き次第(はじとあたまはかきしだい)



