十年一日の如しとは
十年一日の如し
じゅうねんいちじつのごとし
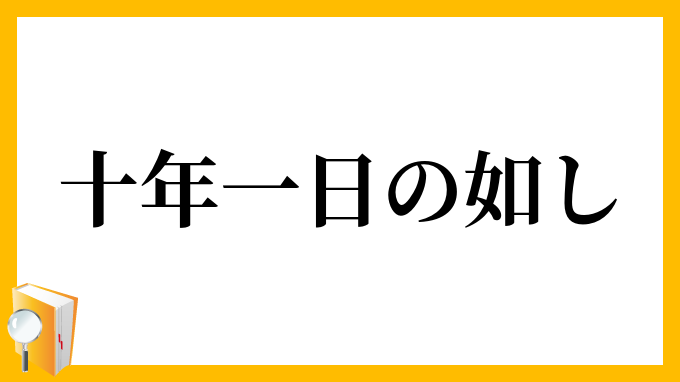
| 言葉 | 十年一日の如し |
|---|---|
| 読み方 | じゅうねんいちじつのごとし |
| 意味 | 長い年月が経っても、少しも変わらず同じ状態である様子。
十年経っても、最初の一日と同じであるとの意から。 |
| 使用語彙 | 一日 / 如し |
| 使用漢字 | 十 / 年 / 一 / 日 / 如 |
「十」を含むことわざ
- 悪妻は六十年の不作(あくさいはろくじゅうねんのふさく)
- 明日の百より今日の五十(あすのひゃくよりきょうのごじゅう)
- 一から十まで(いちからじゅうまで)
- 一日暖めて十日冷やす(いちにちあたためてとおかひやす)
- 一日一字を学べば三百六十字(いちにちいちじをまなべばさんびゃくろくじゅうじ)
- 一を聞いて十を知る(いちをきいてじゅうをしる)
- いやいや三杯十三杯(いやいやさんばいじゅうさんばい)
- うかうか三十きょろきょろ四十(うかうかさんじゅうきょろきょろしじゅう)
- 男は二十五の暁まで育つ(おとこはにじゅうごのあかつきまでそだつ)
- 鬼も十八(おにもじゅうはち)
「年」を含むことわざ
- 商い三年(あきないさんねん)
- 秋の入り日と年寄りはだんだん落ち目が早くなる(あきのいりひととしよりはだんだんおちめがはやくなる)
- 悪妻は百年の不作(あくさいはひゃくねんのふさく)
- 悪妻は六十年の不作(あくさいはろくじゅうねんのふさく)
- 顎振り三年(あごふりさんねん)
- いい年をして(いいとしをして)
- 家を道端に作れば三年成らず(いえをみちばたにつくればさんねんならず)
- 烏賊の甲より年の功(いかのこうよりとしのこう)
- 烏賊の甲より年の劫(いかのこうよりとしのこう)
- 石の上にも三年(いしのうえにもさんねん)
「一」を含むことわざ
- 悪は一旦の事なり(あくはいったんのことなり)
- 朝顔の花一時(あさがおのはないっとき)
- 朝の一時は晩の二時に当たる(あさのひとときはばんのふたときにあたる)
- 薊の花も一盛り(あざみのはなもひとさかり)
- あの世の千日、この世の一日(あのよのせんにち、このよのいちにち)
- 危ない橋も一度は渡れ(あぶないはしもいちどはわたれ)
- 粟一粒は汗一粒(あわひとつぶはあせひとつぶ)
- 板子一枚下は地獄(いたごいちまいしたはじごく)
- 一瓜実に二丸顔(いちうりざねににまるがお)
- 一応も二応も(いちおうもにおうも)
「日」を含むことわざ
- 秋風と夫婦喧嘩は日が入りゃ止む(あきかぜとふうふげんかはひがいりゃやむ)
- 秋の入り日と年寄りはだんだん落ち目が早くなる(あきのいりひととしよりはだんだんおちめがはやくなる)
- 秋の日と娘の子はくれぬようでくれる(あきのひとむすめのこはくれぬようでくれる)
- 秋の日は釣瓶落とし(あきのひはつるべおとし)
- 秋日和半作(あきびよりはんさく)
- 明後日の方(あさってのほう)
- 朝日が西から出る(あさひがにしからでる)
- 明日は明日の風が吹く(あしたはあしたのかぜがふく)
- 明日ありと思う心の仇桜(あすありとおもうこころのあだざくら)
- 明日食う塩辛に今日から水を飲む(あすくうしおからにきょうからみずをのむ)



