馬鹿の一つ覚えとは
馬鹿の一つ覚え
ばかのひとつおぼえ
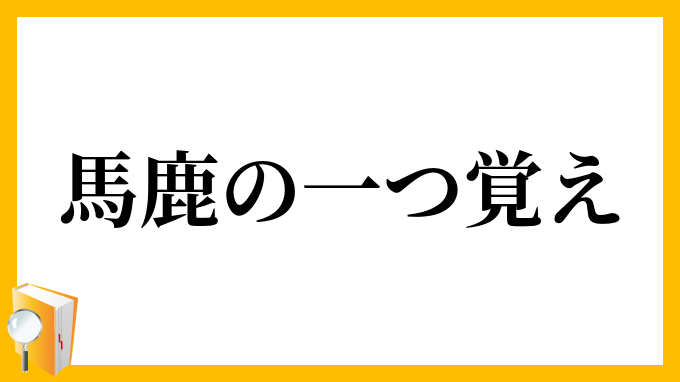
| 言葉 | 馬鹿の一つ覚え |
|---|---|
| 読み方 | ばかのひとつおぼえ |
| 意味 | 愚か者が、たった一つ覚えていることを得意げに振りかざすことをあざけっていう言葉。 |
| 使用語彙 | 馬鹿 / 一つ / 一 / 覚え |
| 使用漢字 | 馬 / 鹿 / 一 / 覚 |
「馬」を含むことわざ
- 朝雨馬に鞍置け(あさあめうまにくらおけ)
- 鞍上人なく、鞍下馬なし(あんじょうひとなく、あんかうまなし)
- 生き馬の目を抜く(いきうまのめをぬく)
- 一番風呂は馬鹿が入る(いちばんぶろはばかがはいる)
- 一匹の馬が狂えば千匹の馬も狂う(いっぴきのうまがくるえばせんびきのうまもくるう)
- 牛は牛連れ、馬は馬連れ(うしはうしづれ、うまはうまづれ)
- 牛も千里馬も千里(うしもせんりうまもせんり)
- 牛を馬に乗り換える(うしをうまにのりかえる)
- 内で掃除せぬ馬は外で毛を振る(うちでそうじせぬうまはそとでけをふる)
- 馬が合う(うまがあう)
「鹿」を含むことわざ
- 秋の鹿は笛に寄る(あきのしかはふえによる)
- 一番風呂は馬鹿が入る(いちばんぶろはばかがはいる)
- 馬を鹿(うまをしか)
- 親馬鹿子馬鹿(おやばかこばか)
- 鹿島立ち(かしまだち)
- 火事場の馬鹿力(かじばのばかぢから)
- 金があれば馬鹿も旦那(かねがあればばかもだんな)
- 空世辞は馬鹿を嬉しがらせる(からせじはばかをうれしがらせる)
- 下種の一寸、のろまの三寸、馬鹿の開けっ放し(げすのいっすん、のろまのさんずん、ばかのあけっぱなし)
- 桜折る馬鹿、柿折らぬ馬鹿(さくらおるばか、かきおらぬばか)
「一」を含むことわざ
- 悪は一旦の事なり(あくはいったんのことなり)
- 朝顔の花一時(あさがおのはなひととき)
- 朝の一時は晩の二時に当たる(あさのひとときはばんのふたときにあたる)
- 薊の花も一盛り(あざみのはなもひとさかり)
- あの世の千日、この世の一日(あのよのせんにち、このよのいちにち)
- 危ない橋も一度は渡れ(あぶないはしもいちどはわたれ)
- 粟一粒は汗一粒(あわひとつぶはあせひとつぶ)
- 板子一枚下は地獄(いたごいちまいしたはじごく)
- 一瓜実に二丸顔(いちうりざねににまるがお)
- 一応も二応も(いちおうもにおうも)



