馬鹿な子ほど可愛いとは
馬鹿な子ほど可愛い
ばかなこほどかわいい
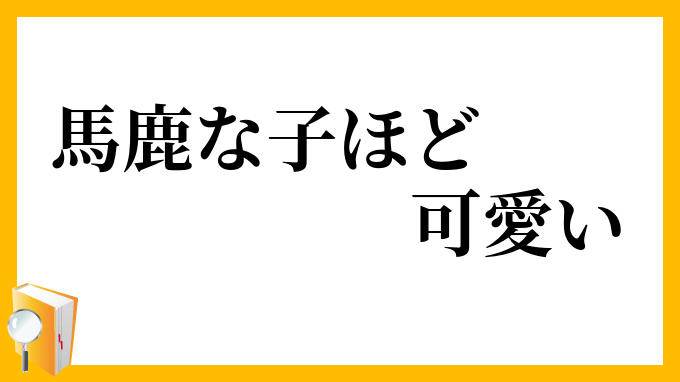
| 言葉 | 馬鹿な子ほど可愛い |
|---|---|
| 読み方 | ばかなこほどかわいい |
| 意味 | 親にとっては、賢い子より愚かな子のほうがふびんでかわいいということ。 |
| 場面用途 | 親子 / 親族 |
| 類句 | 悪い子ほど可愛い |
| 鈍な子ほど可愛い | |
| 使用語彙 | 馬鹿 / 子 |
| 使用漢字 | 馬 / 鹿 / 子 / 可 / 愛 |
「馬」を含むことわざ
- 秋高く馬肥ゆ(あきたかくうまこゆ)
- 朝雨馬に鞍置け(あさあめうまにくらおけ)
- 鞍上人なく、鞍下馬なし(あんじょうひとなく、あんかうまなし)
- 生き馬の目を抜く(いきうまのめをぬく)
- 一番風呂は馬鹿が入る(いちばんぶろはばかがはいる)
- 一匹の馬が狂えば千匹の馬も狂う(いっぴきのうまがくるえばせんびきのうまもくるう)
- 牛は牛連れ、馬は馬連れ(うしはうしづれ、うまはうまづれ)
- 牛も千里馬も千里(うしもせんりうまもせんり)
- 牛を馬に乗り換える(うしをうまにのりかえる)
- 内で掃除せぬ馬は外で毛を振る(うちでそうじせぬうまはそとでけをふる)
「鹿」を含むことわざ
- 秋の鹿は笛に寄る(あきのしかはふえによる)
- 一番風呂は馬鹿が入る(いちばんぶろはばかがはいる)
- 馬を鹿(うまをしか)
- 親馬鹿子馬鹿(おやばかこばか)
- 鹿島立ち(かしまだち)
- 火事場の馬鹿力(かじばのばかぢから)
- 金があれば馬鹿も旦那(かねがあればばかもだんな)
- 空世辞は馬鹿を嬉しがらせる(からせじはばかをうれしがらせる)
- 下種の一寸、のろまの三寸、馬鹿の開けっ放し(げすのいっすん、のろまのさんずん、ばかのあけっぱなし)
- 桜折る馬鹿、柿折らぬ馬鹿(さくらおるばか、かきおらぬばか)
「子」を含むことわざ
- 赤子のうちは七国七里の者に似る(あかごのうちはななくにななさとのものににる)
- 赤子の腕を捩じる(あかごのうでをねじる)
- 赤子の手をねじる(あかごのてをねじる)
- 赤子の手を捩じるよう(あかごのてをねじるよう)
- 赤子の手を捻る(あかごのてをひねる)
- 赤子の手を捻るよう(あかごのてをひねるよう)
- 赤子は泣き泣き育つ(あかごはなきなきそだつ)
- 赤子を裸にしたよう(あかごをはだかにしたよう)
- 秋茄子は嫁に食わすな(あきなすはよめにくわすな)
- 秋の日と娘の子はくれぬようでくれる(あきのひとむすめのこはくれぬようでくれる)
「可」を含むことわざ
- 朝に道を聞かば夕べに死すとも可なり(あしたにみちをきかばゆうべにしすともかなり)
- 可惜口に風ひかす(あったらくちにかぜをひかす)
- 可もなく不可もなし(かもなくふかもなし)
- 可愛さ余って憎さが百倍(かわいさあまってにくさがひゃくばい)
- 可愛さ余って憎さ百倍(かわいさあまってにくさひゃくばい)
- 朽木は雕る可からず(きゅうぼくはえるべからず)
- 不可能という言葉は我が辞書にはない(ふかのうということばはわがじしょにはない)
- 孫は子より可愛い(まごはこよりかわいい)
- 孫は子よりも可愛い(まごはこよりもかわいい)



