目には青葉、山時鳥、初鰹とは
目には青葉、山時鳥、初鰹
めにはあおば、やまほととぎす、はつがつお
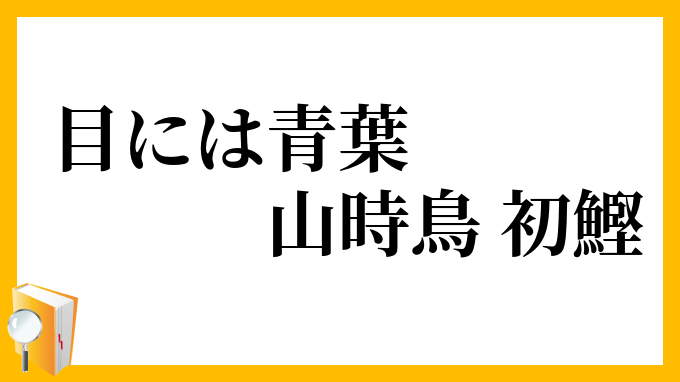
| 言葉 | 目には青葉、山時鳥、初鰹 |
|---|---|
| 読み方 | めにはあおば、やまほととぎす、はつがつお |
| 意味 | 初夏のさわやかな風物を並べたことば。江戸時代の俳人山口素堂の句。 |
| 場面用途 | 夏 / 季節 |
| 使用語彙 | 青葉 / 青 / 葉 / 初鰹 / 初 |
| 使用漢字 | 目 / 青 / 葉 / 山 / 時 / 鳥 / 初 / 鰹 |
「目」を含むことわざ
- 青葉は目の薬(あおばはめのくすり)
- 秋の入り日と年寄りはだんだん落ち目が早くなる(あきのいりひととしよりはだんだんおちめがはやくなる)
- 商人の子は算盤の音で目を覚ます(あきんどのこはそろばんのおとでめをさます)
- 麻殻に目鼻をつけたよう(あさがらにめはなをつけたよう)
- 朝題目に宵念仏(あさだいもくによいねんぶつ)
- 網の目に風たまらず(あみのめにかぜたまらず)
- 網の目に風たまる(あみのめにかぜたまる)
- 網の目を潜る(あみのめをくぐる)
- いい目が出る(いいめがでる)
- いい目を見る(いいめをみる)
「青」を含むことわざ
- 青い鳥(あおいとり)
- 青柿が熟柿弔う(あおがきがじゅくしとむらう)
- 青くなる(あおくなる)
- 青写真を描く(あおじゃしんをえがく)
- 青筋を立てる(あおすじをたてる)
- 青田買い(あおたがい)
- 青菜に塩(あおなにしお)
- 青菜は男に見せな(あおなはおとこにみせな)
- 青二才(あおにさい)
- 青は藍より出でて藍より青し(あおはあいよりいでてあいよりあおし)
「葉」を含むことわざ
- 合言葉にする(あいことばにする)
- 青葉は目の薬(あおばはめのくすり)
- 秋葉山から火事(あきばさんからかじ)
- 後から剝げる正月言葉(あとからはげるしょうがつことば)
- 石が流れて木の葉が沈む(いしがながれてこのはがしずむ)
- 一葉落ちて天下の秋を知る(いちようおちててんかのあきをしる)
- 売り言葉に買い言葉(うりことばにかいことば)
- 返す言葉がない(かえすことばがない)
- 顔に紅葉を散らす(かおにもみじをちらす)
- 桐一葉(きりひとは)
「山」を含むことわざ
- 秋葉山から火事(あきばさんからかじ)
- 後は野となれ山となれ(あとはのとなれやまとなれ)
- 何れを見ても山家育ち(いずれをみてもやまがそだち)
- 一度焼けた山は二度は焼けぬ(いちどやけたやまはにどはやけぬ)
- 一目山随徳寺(いちもくさんずいとくじ)
- 海に千年山に千年(うみにせんねんやまにせんねん)
- 海の物とも山の物ともつかぬ(うみのものともやまのものともつかぬ)
- 円石を千仞の山に転ず(えんせきをせんじんのやまにてんず)
- 驚き、桃の木、山椒の木(おどろき、もものき、さんしょのき)
- お山の大将(おやまのたいしょう)
「時」を含むことわざ
- 挨拶は時の氏神(あいさつはときのうじがみ)
- 朝顔の花一時(あさがおのはなひととき)
- 朝の一時は晩の二時に当たる(あさのひとときはばんのふたときにあたる)
- あの声で蜥蜴食らうか時鳥(あのこえでとかげくらうかほととぎす)
- ある時は米の飯(あるときはこめのめし)
- ある時払いの催促なし(あるときばらいのさいそくなし)
- いざという時(いざというとき)
- 何時にない(いつにない)
- 今を時めく(いまをときめく)
- 飢えたる時は食を択ばず(うえたるときはしょくをえらばず)
「鳥」を含むことわざ
- 青い鳥(あおいとり)
- 足下から鳥が立つ(あしもとからとりがたつ)
- 飛鳥川の淵瀬(あすかがわのふちせ)
- あだし野の露、鳥辺野の煙(あだしののつゆ、とりべののけむり)
- あの声で蜥蜴食らうか時鳥(あのこえでとかげくらうかほととぎす)
- 越鳥南枝に巣くい、胡馬北風に嘶く(えっちょうなんしにすくい、こばほくふうにいななく)
- 同じ羽の鳥は集まるものだ(おなじはねのとりはあつまるものだ)
- 霞に千鳥(かすみにちどり)
- 金さえあれば飛ぶ鳥も落ちる(かねさえあればとぶとりもおちる)
- 閑古鳥が鳴く(かんこどりがなく)
「初」を含むことわざ
- 最初で最後(さいしょでさいご)
- 初心に返る(しょしんにかえる)
- 初心忘るべからず(しょしんわするべからず)
- 初日が出る(しょにちがでる)
- 短気は未練の初め(たんきはみれんのはじめ)
- 初めの勝ちは糞勝ち(はじめのかちはくそがち)
- 初物七十五日(はつものしちじゅうごにち)
- 人の初事は咎めぬもの(ひとのういごとはとがめぬもの)
「鰹」を含むことわざ
- 猫が肥えれば鰹節が痩せる(ねこがこえればかつおぶしがやせる)
- 猫に鰹節(ねこにかつおぶし)
- 猫を追うより鰹節を隠せ(ねこをおうよりかつおぶしをかくせ)
- 目には青葉、山時鳥、初鰹(めにはあおば、やまほととぎす、はつがつお)



