頼めば越後から米搗きにも来るとは
頼めば越後から米搗きにも来る
たのめばえちごからこめつきにもくる
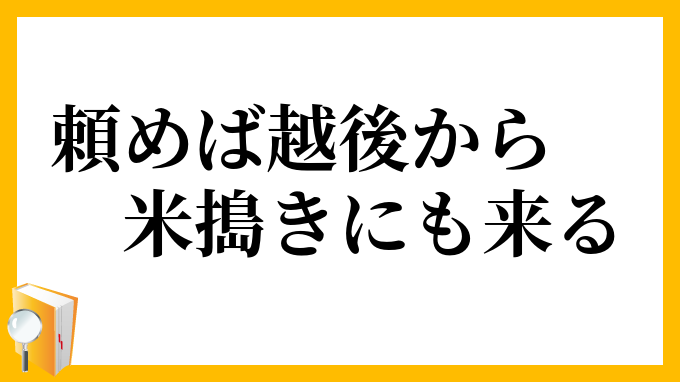
| 言葉 | 頼めば越後から米搗きにも来る |
|---|---|
| 読み方 | たのめばえちごからこめつきにもくる |
| 意味 | 真心をつくして頼めば、人は嫌とは言えないもので、難しいことであっても承知してくれるというたとえ。
「越後」は、現在の新潟県。ここでは遠いの場所のたとえ。 心から頼めば、遠い場所からでも米搗きに来てくれるとの意から。 |
| 類句 | 頼むと頼まれては犬も木へ登る(たのむとたのまれてはいぬもきへのぼる) |
| 使用漢字 | 頼 / 越 / 後 / 米 / 搗 / 来 |
「頼」を含むことわざ
- 鬼も頼めば人食わず(おにもたのめばひとくわず)
- 数を頼む(かずをたのむ)
- 叶わぬ時の神頼み(かなわぬときのかみだのみ)
- 苦しい時の神頼み(くるしいときのかみだのみ)
- 衆を頼む(しゅうをたのむ)
- 数を頼む(すうをたのむ)
- 多勢を頼む群鴉(たぜいをたのむむらがらす)
- 頼みの綱(たのみのつな)
- 頼みの綱も切れ果てる(たのみのつなもきれはてる)
- 頼む木陰に雨が漏る(たのむこかげにあめがもる)
「越」を含むことわざ
- 当て事と越中褌は向こうから外れる(あてごととえっちゅうふんどしはむこうからはずれる)
- 越鳥南枝に巣くい、胡馬北風に嘶く(えっちょうなんしにすくい、こばほくふうにいななく)
- 越鳥南枝に巣くう(えっちょうなんしにすくう)
- 越王、怒蛙に式す(えつおう、どあにしょくす)
- 江戸っ子は宵越しの銭は使わぬ(えどっこはよいごしのぜにはつかわぬ)
- 川越して宿とれ(かわこしてやどとれ)
- 先を越す(さきをこす)
- 信心過ぎて極楽を通り越す(しんじんすぎてごくらくをとおりこす)
- 峠を越す(とうげをこす)
「後」を含むことわざ
- 明後日の方(あさってのほう)
- 後足で砂をかける(あとあしですなをかける)
- 後味が悪い(あとあじがわるい)
- 後押しをする(あとおしをする)
- 後から剝げる正月言葉(あとからはげるしょうがつことば)
- 後がない(あとがない)
- 後釜に据える(あとがまにすえる)
- 後釜に座る(あとがまにすわる)
- 後釜に据わる(あとがまにすわる)
- 後口が悪い(あとくちがわるい)
「米」を含むことわざ
- 足の裏の米粒をこそげる(あしのうらのこめつぶをこそげる)
- ある時は米の飯(あるときはこめのめし)
- いつも月夜に米の飯(いつもつきよにこめのめし)
- 思し召しより米の飯(おぼしめしよりこめのめし)
- 米食った犬が叩かれずに糠食った犬が叩かれる(こめくったいぬがたたかれずにぬかくったいぬがたたかれる)
- 米の飯と女は白いほどよい(こめのめしとおんなはしろいほどよい)
- 米の飯と天道様はどこへ行っても付いて回る(こめのめしとてんとうさまはどこへいってもついてまわる)
- 米の飯より思し召し(こめのめしよりおぼしめし)
- 米を数えて炊ぐ(こめをかぞえてかしぐ)
- 五斗米のために腰を折る(ごとべいのためにこしをおる)
「搗」を含むことわざ
- 頼めば越後から米搗きにも来る(たのめばえちごからこめつきにもくる)
- 提灯で餅を搗く(ちょうちんでもちをつく)
- 搗いた餅より心持ち(ついたもちよりこころもち)
- 搗き臼で茶漬け(つきうすでちゃづけ)



