百日の説法、屁一つとは
百日の説法、屁一つ
ひゃくにちのせっぽう、へひとつ
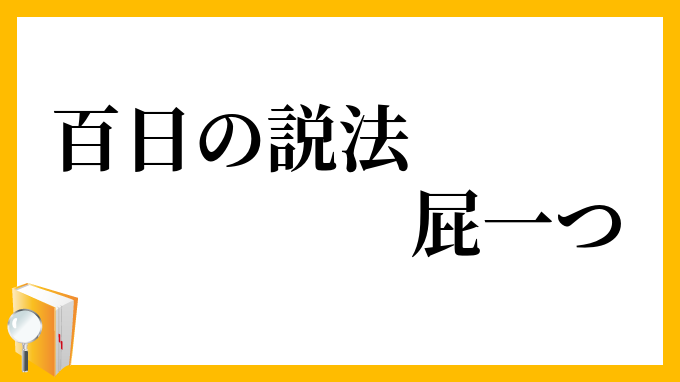
| 言葉 | 百日の説法、屁一つ |
|---|---|
| 読み方 | ひゃくにちのせっぽう、へひとつ |
| 意味 | 長い間苦労してきたことが、わずかな失敗によって無駄になってしまうことのたとえ。
百日間も説いてきた説法も、お坊さんのおならを一つでありがたみがなくなってしまうとの意から。 |
| 類句 | 九仞の功を一簣に虧く(きゅうじんのこうをいっきにかく) |
| 磯際で船を破る(いそぎわでふねをやぶる) | |
| 草履履き際で仕損じる(ぞうりはきぎわでしそんじる) | |
| 使用語彙 | 説法 / 屁 / 一つ / 一 |
| 使用漢字 | 百 / 日 / 説 / 法 / 屁 / 一 |
「百」を含むことわざ
- 悪妻は百年の不作(あくさいはひゃくねんのふさく)
- 朝起き千両、夜起き百両(あさおきせんりょう、よおきひゃくりょう)
- 明日の百より今日の五十(あすのひゃくよりきょうのごじゅう)
- 一日一字を学べば三百六十字(いちにちいちじをまなべばさんびゃくろくじゅうじ)
- 一文惜しみの百知らず(いちもんおしみのひゃくしらず)
- 一犬影に吠ゆれば百犬声に吠ゆ(いっけんかげにほゆればひゃっけんこえにほゆ)
- 嘘八百(うそはっぴゃく)
- 嘘八百を並べる(うそはっぴゃくをならべる)
- 江戸は八百八町、大坂は八百八橋(えどははっぴゃくやちょう、おおさかははっぴゃくやばし)
- 男は裸百貫(おとこははだかひゃっかん)
「日」を含むことわざ
- 秋風と夫婦喧嘩は日が入りゃ止む(あきかぜとふうふげんかはひがいりゃやむ)
- 秋の入り日と年寄りはだんだん落ち目が早くなる(あきのいりひととしよりはだんだんおちめがはやくなる)
- 秋の日と娘の子はくれぬようでくれる(あきのひとむすめのこはくれぬようでくれる)
- 秋の日は釣瓶落とし(あきのひはつるべおとし)
- 秋日和半作(あきびよりはんさく)
- 明後日の方(あさってのほう)
- 朝日が西から出る(あさひがにしからでる)
- 明日は明日の風が吹く(あしたはあしたのかぜがふく)
- 明日ありと思う心の仇桜(あすありとおもうこころのあだざくら)
- 明日食う塩辛に今日から水を飲む(あすくうしおからにきょうからみずをのむ)
「説」を含むことわざ
- 女は己を説ぶ者のために容づくる(おんなはおのれをよろこぶもののためにかたちづくる)
- 機に因りて法を説け(きによりてほうをとけ)
- 釈迦に説法(しゃかにせっぽう)
- 釈迦に説法、孔子に悟道(しゃかにせっぽう、こうしにごどう)
- 事実は小説よりも奇なり(じじつはしょうせつよりもきなり)
- 談義説法は出家の生計(だんぎせっぽうはしゅっけのせいけい)
- 談義説法は出家の身過ぎ(だんぎせっぽうはしゅっけのみすぎ)
- 痴人の前に夢を説く(ちじんのまえにゆめをとく)
- 痴人夢を説く(ちじんゆめをとく)
- 人を見て法を説け(にんをみてほうをとけ)
「法」を含むことわざ
- 悪法もまた法なり(あくほうもまたほうなり)
- 置き酌失礼、持たぬが不調法(おきじゃくしつれい、もたぬがぶちょうほう)
- 機に因りて法を説け(きによりてほうをとけ)
- 弘法にも筆の誤り(こうぼうにもふでのあやまり)
- 弘法筆を択ばず(こうぼうふでをえらばず)
- 士族の商法(しぞくのしょうほう)
- 釈迦に説法(しゃかにせっぽう)
- 釈迦に説法、孔子に悟道(しゃかにせっぽう、こうしにごどう)
- 春秋の筆法(しゅんじゅうのひっぽう)
- 正法に不思議なし(しょうほうにふしぎなし)
「屁」を含むことわざ
- 鼬の最後っ屁(いたちのさいごっぺ)
- 河童の屁(かっぱのへ)
- 沈香も焚かず、屁もひらず(じんこうもたかず、へもひらず)
- 屁と火事は元から騒ぐ(へとかじはもとからさわぐ)
- 屁とも思わない(へともおもわない)
- 屁の河童(へのかっぱ)
- 屁を放って尻窄める(へをひってしりすぼめる)



