大声は里耳に入らずとは
大声は里耳に入らず
たいせいはりじにいらず
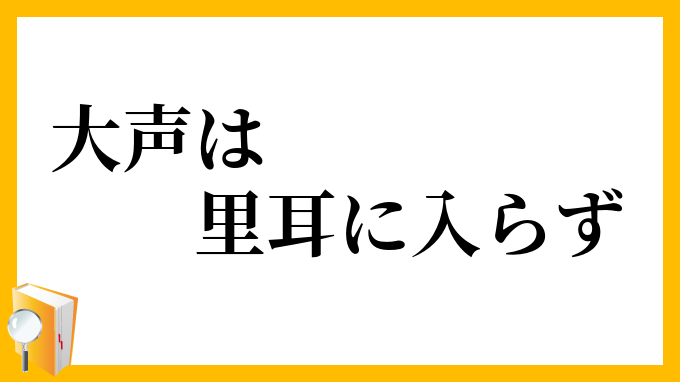
| 言葉 | 大声は里耳に入らず |
|---|---|
| 読み方 | たいせいはりじにいらず |
| 意味 | 高尚な理論は俗人にはなかなか理解されにくいということ。
「大声」は高尚な音楽、「里耳」は俗人の耳のこと。 高尚な音楽は俗人にはわからないとの意から。 |
| 出典 | 『荘子』天地 |
| 使用漢字 | 大 / 声 / 里 / 耳 / 入 |
「大」を含むことわざ
- 諍いをしいしい腹を大きくし(いさかいをしいしいはらをおおきくし)
- 井の中の蛙大海を知らず(いのなかのかわずたいかいをしらず)
- 上を下への大騒ぎ(うえをしたへのおおさわぎ)
- 独活の大木(うどのたいぼく)
- 瓜の皮は大名に剝かせよ、柿の皮は乞食に剝かせよ(うりのかわはだいみょうにむかせよ、かきのかわはこじきにむかせよ)
- 江戸っ子の往き大名還り乞食(えどっこのゆきだいみょうかえりこじき)
- 江戸は八百八町、大坂は八百八橋(えどははっぴゃくやちょう、おおさかははっぴゃくやばし)
- お家の一大事(おいえのいちだいじ)
- 大当たりを取る(おおあたりをとる)
- 大嘘はつくとも小嘘はつくな(おおうそはつくともこうそはつくな)
「声」を含むことわざ
- 相手見てからの喧嘩声(あいてみてからのけんかごえ)
- 空き家で声嗄らす(あきやでこえからす)
- あの声で蜥蜴食らうか時鳥(あのこえでとかげくらうかほととぎす)
- 一犬影に吠ゆれば百犬声に吠ゆ(いっけんかげにほゆればひゃっけんこえにほゆ)
- 産声を上げる(うぶごえをあげる)
- お声が掛かる(おこえがかかる)
- 蚊の鳴くような声(かのなくようなこえ)
- 楽屋で声を嗄らす(がくやでこえをからす)
- 黄色い声(きいろいこえ)
- 君子は交わり絶ゆとも悪声を出さず(くんしはまじわりたゆともあくせいをださず)
「里」を含むことわざ
- 赤子のうちは七国七里の者に似る(あかごのうちはななくにななさとのものににる)
- 悪事千里を走る(あくじせんりをはしる)
- 朝茶は七里帰っても飲め(あさちゃはしちりかえってものめ)
- 牛も千里馬も千里(うしもせんりうまもせんり)
- 縁あれば千里(えんあればせんり)
- お里が知れる(おさとがしれる)
- 門松は冥土の旅の一里塚(かどまつはめいどのたびのいちりづか)
- 好事門を出でず、悪事千里を行く(こうじもんをいでず、あくじせんりをいく)
- 酒屋へ三里、豆腐屋へ二里(さかやへさんり、とうふやへにり)
- 囁き千里(ささやきせんり)
「耳」を含むことわざ
- 馬の耳に風(うまのみみにかぜ)
- 馬の耳に念仏(うまのみみにねんぶつ)
- 壁に耳あり障子に目あり(かべにみみありしょうじにめあり)
- 聞き耳を立てる(ききみみをたてる)
- 牛耳を執る(ぎゅうじをとる)
- 口耳の学(こうじのがく)
- 小耳に挟む(こみみにはさむ)
- 笊耳(ざるみみ)
- 杓子は耳搔きにならず(しゃくしはみみかきにならず)
- 耳順(じじゅん)



