君子は交わり絶ゆとも悪声を出さずとは
君子は交わり絶ゆとも悪声を出さず
くんしはまじわりたゆともあくせいをださず
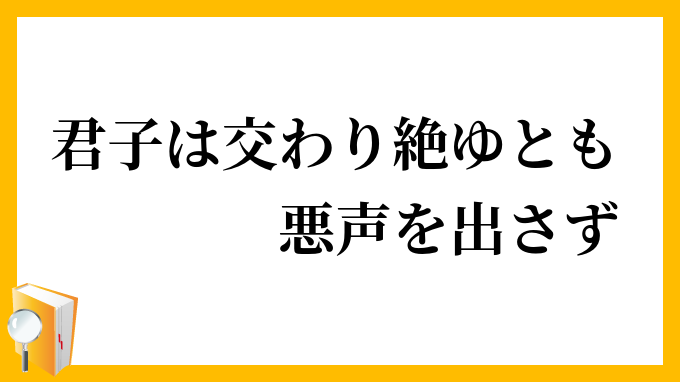
| 言葉 | 君子は交わり絶ゆとも悪声を出さず |
|---|---|
| 読み方 | くんしはまじわりたゆともあくせいをださず |
| 意味 | 徳のある人は人と絶交することがあっても相手の悪口は決して言わないということ。 |
| 使用語彙 | 君子 / 交わり / 悪声 |
| 使用漢字 | 君 / 子 / 交 / 絶 / 悪 / 声 / 出 |
「君」を含むことわざ
- 一天万乗の君(いってんばんじょうのきみ)
- 王は君臨すれども統治せず(おうはくんりんすれどもとうちせず)
- 君、君たらずと雖も臣は臣たらざるべからず(きみ、きみたらずといえどもしんはしんたらざるべからず)
- 君、辱めらるれば臣死す(きみ、はずかしめらるればしんしす)
- 君を思うも身を思う(きみをおもうもみをおもう)
- 君子、危うきに近寄らず(くんし、あやうきにちかよらず)
- 君子に三戒あり(くんしにさんかいあり)
- 君子に三楽あり(くんしにさんらくあり)
- 君子の過ちは日月の食のごとし(くんしのあやまちはじつげつのしょくのごとし)
- 君子の三楽(くんしのさんらく)
「子」を含むことわざ
- 赤子のうちは七国七里の者に似る(あかごのうちはななくにななさとのものににる)
- 赤子の腕を捩じる(あかごのうでをねじる)
- 赤子の手をねじる(あかごのてをねじる)
- 赤子の手を捩じるよう(あかごのてをねじるよう)
- 赤子の手を捻る(あかごのてをひねる)
- 赤子の手を捻るよう(あかごのてをひねるよう)
- 赤子は泣き泣き育つ(あかごはなきなきそだつ)
- 赤子を裸にしたよう(あかごをはだかにしたよう)
- 秋茄子は嫁に食わすな(あきなすはよめにくわすな)
- 秋の日と娘の子はくれぬようでくれる(あきのひとむすめのこはくれぬようでくれる)
「交」を含むことわざ
- 交喙の嘴(いすかのはし)
- 一戦を交える(いっせんをまじえる)
- 干戈を交える(かんかをまじえる)
- 管鮑の交わり(かんぽうのまじわり)
- 金石の交わり(きんせきのまじわり)
- 君子の交わりは淡きこと水のごとし(くんしのまじわりはあわきことみずのごとし)
- 膠漆の交わり(こうしつのまじわり)
- 口頭の交わり(こうとうのまじわり)
- 雑魚の魚交じり(ざこのととまじり)
「絶」を含むことわざ
- 跡を絶たない(あとをたたない)
- 韋編三度絶つ(いへんみたびたつ)
- 舌の剣は命を絶つ(したのつるぎはいのちをたつ)
- 消息を絶つ(しょうそくをたつ)
- 絶景というは樽肴ありてこそ(ぜっけいというはたるさかなありてこそ)
- 想像を絶する(そうぞうをぜっする)
- 塵を絶つ(ちりをたつ)
- 波風が絶えない(なみかぜがたえない)
- 根絶やしにする(ねだやしにする)
「悪」を含むことわざ
- 合性が悪い(あいしょうがわるい)
- 相性が悪い(あいしょうがわるい)
- 愛は憎悪の始め(あいはぞうおのはじめ)
- 悪縁契り深し(あくえんちぎりふかし)
- 悪妻は百年の不作(あくさいはひゃくねんのふさく)
- 悪妻は六十年の不作(あくさいはろくじゅうねんのふさく)
- 悪事、千里を走る(あくじ、せんりをはしる)
- 悪事、身にかえる(あくじ、みにかえる)
- 悪事、千里を行く(あくじせんりをいく)
- 悪獣もなおその類を思う(あくじゅうもなおそのるいをおもう)
「声」を含むことわざ
- 相手見てからの喧嘩声(あいてみてからのけんかごえ)
- 空き家で声嗄らす(あきやでこえからす)
- あの声で蜥蜴食らうか時鳥(あのこえでとかげくらうかほととぎす)
- 一犬影に吠ゆれば百犬声に吠ゆ(いっけんかげにほゆればひゃっけんこえにほゆ)
- 産声を上げる(うぶごえをあげる)
- お声が掛かる(おこえがかかる)
- 蚊の鳴くような声(かのなくようなこえ)
- 楽屋で声を嗄らす(がくやでこえをからす)
- 黄色い声(きいろいこえ)



