憎まれっ子世に憚るとは
憎まれっ子世に憚る
にくまれっこよにはばかる
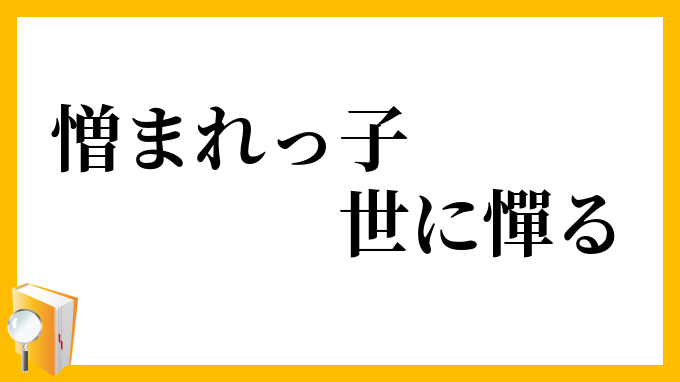
| 言葉 | 憎まれっ子世に憚る |
|---|---|
| 読み方 | にくまれっこよにはばかる |
| 意味 | 人から憎まれるような者にかぎって、世の中では幅をきかせているということ。
「憚る」とは幅をきかすこと。 「憎まれっ子」は「憎まれ子」ともいう。 また、「憎まれ子国にはびこる」「憎まれ子国にはだかる」「憎まれ子世に出ず」「憎まれ者世に憚る」などともいう。 |
| 異形 | 憎まれ子国にはびこる(にくまれこくににはびこる) |
| 憎まれ子国にはだかる(にくまれこくににはだかる) | |
| 憎まれ子世に出ず(にくまれこよにいず) | |
| 憎まれ者世に憚る(にくまれものよにはばかる) | |
| 類句 | 呪うに死なず(のろうにしなず) |
| 使用語彙 | 憎まれっ子 / 子 / 世 |
| 使用漢字 | 憎 / 子 / 世 / 憚 / 国 / 出 / 者 |
「憎」を含むことわざ
- 愛多ければ憎しみ至る(あいおおければにくしみいたる)
- 愛は憎悪の始め(あいはぞうおのはじめ)
- 一に褒められ二に憎まれ三に惚れられ四に風邪ひく(いちにほめられにににくまれさんにほれられしにかぜひく)
- 可愛さ余って憎さが百倍(かわいさあまってにくさがひゃくばい)
- 罪を憎んで人を憎まず(つみをにくんでひとをにくまず)
- 七つ七里憎まれる(ななつななさとにくまれる)
- 憎い憎いはかわいいの裏(にくいにくいはかわいいのうら)
- 憎さも憎し(にくさもにくし)
- 憎まれ口を叩く(にくまれぐちをたたく)
「子」を含むことわざ
- 赤子のうちは七国七里の者に似る(あかごのうちはななくにななさとのものににる)
- 赤子の腕を捩じる(あかごのうでをねじる)
- 赤子の手を捻る(あかごのてをひねる)
- 赤子は泣き泣き育つ(あかごはなきなきそだつ)
- 赤子を裸にしたよう(あかごをはだかにしたよう)
- 秋茄子は嫁に食わすな(あきなすはよめにくわすな)
- 秋の日と娘の子はくれぬようでくれる(あきのひとむすめのこはくれぬようでくれる)
- 商人の子は算盤の音で目を覚ます(あきんどのこはそろばんのおとでめをさます)
- 熱火子に払う(あつびこにはらう)
- 後先息子に中娘(あとさきむすこになかむすめ)
「世」を含むことわざ
- 明日知らぬ世(あすしらぬよ)
- あの世の千日、この世の一日(あのよのせんにち、このよのいちにち)
- 石の物言う世の中(いしのものいうよのなか)
- 一世を風靡する(いっせいをふうびする)
- いらぬお世話の蒲焼(いらぬおせわのかばやき)
- 有為転変は世の習い(ういてんぺんはよのならい)
- 浮世の風(うきよのかぜ)
- 浮世は衣装七分(うきよはいしょうしちぶ)
- 浮世は回り持ち(うきよはまわりもち)
- 浮世は夢(うきよはゆめ)
「憚」を含むことわざ
- 過ちては改むるに憚ること勿れ(あやまちてはあらたむるにはばかることなかれ)
- 他聞を憚る(たぶんをはばかる)
- 憎まれっ子世に憚る(にくまれっこよにはばかる)
- 人目を憚る(ひとめをはばかる)
- 世を憚る(よをはばかる)
「国」を含むことわざ
- 赤子のうちは七国七里の者に似る(あかごのうちはななくにななさとのものににる)
- 家に鼠、国に盗人(いえにねずみ、くににぬすびと)
- 一国一城の主(いっこくいちじょうのあるじ)
- 華胥の国に遊ぶ(かしょのくににあそぶ)
- 国に盗人、家に鼠(くににぬすびと、いえにねずみ)
- 国乱れて忠臣見る(くにみだれてちゅうしんあらわる)
- 国破れて山河在り(くにやぶれてさんがあり)
- 言葉は国の手形(ことばはくにのてがた)
- 三国一(さんごくいち)
- 修身斉家治国平天下(しゅうしんせいかちこくへいてんか)
「出」を含むことわざ
- 愛出ずる者は愛返り、福往く者は福来る(あいいずるものはあいかえり、ふくゆくものはふくきたる)
- 愛は小出しにせよ(あいはこだしにせよ)
- 青は藍より出でて藍より青し(あおはあいよりいでてあいよりあおし)
- 垢は擦るほど出る、あらは探すほど出る(あかはこするほどでる、あらはさがすほどでる)
- 明るみに出る(あかるみにでる)
- 顎を出す(あごをだす)
- 朝日が西から出る(あさひがにしからでる)
- 足が出る(あしがでる)
- 足を出す(あしをだす)
- 仇も情けも我が身より出る(あだもなさけもわがみよりでる)
「者」を含むことわざ
- 愛出ずる者は愛返り、福往く者は福来る(あいいずるものはあいかえり、ふくゆくものはふくきたる)
- 青表紙を叩いた者にはかなわぬ(あおびょうしをたたいたものにはかなわぬ)
- 赤子のうちは七国七里の者に似る(あかごのうちはななくにななさとのものににる)
- 垢で死んだ者はない(あかでしんだものはない)
- 当たった者のふの悪さ(あたったもののふのわるさ)
- 新たに沐する者は必ず冠を弾く(あらたにもくするものはかならずかんむりをはじく)
- 医者が取るか坊主が取るか(いしゃがとるかぼうずがとるか)
- 医者寒からず儒者寒し(いしゃさむからずじゅしゃさむし)
- 医者上手にかかり下手(いしゃじょうずにかかりべた)
- 医者と味噌は古いほどよい(いしゃとみそはふるいほどよい)



