無精者の一時働きとは
無精者の一時働き
ぶしょうもののいっときばたらき
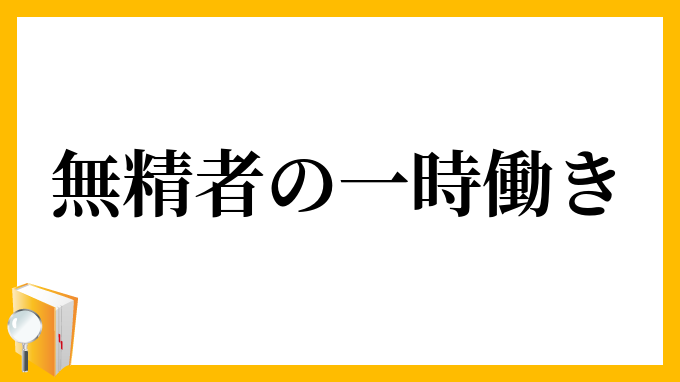
| 言葉 | 無精者の一時働き |
|---|---|
| 読み方 | ぶしょうもののいっときばたらき |
| 意味 | いつも怠けている者が、急に思い立って働いても、一時的だということ。また、そういう者をあざけっていう言葉。 |
| 類句 | 無精者の節句働き |
| 怠け者の節句働き(なまけもののせっくはたらき) | |
| 使用語彙 | 一時 |
| 使用漢字 | 無 / 精 / 者 / 一 / 時 / 働 |
「無」を含むことわざ
- 有って地獄、無くて極楽(あってじごく、なくてごくらく)
- 有っても苦労、無くても苦労(あってもくろう、なくてもくろう)
- 有るか無きか(あるかなきか)
- 有無相通じる(うむあいつうじる)
- 有無を言わせず(うむをいわせず)
- 遠慮は無沙汰(えんりょはぶさた)
- 応接に暇が無い(おうせつにいとまがない)
- 奥行きが無い(おくゆきがない)
- 音沙汰が無い(おとざたがない)
- 親の意見と茄子の花は千に一つも無駄はない(おやのいけんとなすびのはなはせんにひとつもむだはない)
「精」を含むことわざ
- 鰯で精進落ち(いわしでしょうじんおち)
- 健全なる精神は健全なる身体に宿る(けんぜんなるせいしんはけんぜんなるしんたいにやどる)
- 精魂を傾ける(せいこんをかたむける)
- 精彩を放つ(せいさいをはなつ)
- 精神一到、何事か成らざらん(せいしんいっとう、なにごとかならざらん)
- 精を出す(せいをだす)
- 丹精を込める(たんせいをこめる)
- 丹精を凝らす(たんせいをこらす)
- 丹精を尽くす(たんせいをつくす)
- 猫の精進(ねこのしょうじん)
「者」を含むことわざ
- 愛出ずる者は愛返り、福往く者は福来る(あいいずるものはあいかえり、ふくゆくものはふくきたる)
- 青表紙を叩いた者にはかなわぬ(あおびょうしをたたいたものにはかなわぬ)
- 赤子のうちは七国七里の者に似る(あかごのうちはななくにななさとのものににる)
- 垢で死んだ者はない(あかでしんだものはない)
- 悪女の賢者ぶり(あくじょのけんじゃぶり)
- 当たった者のふの悪さ(あたったもののふのわるさ)
- 新たに沐する者は必ず冠を弾く(あらたにもくするものはかならずかんむりをはじく)
- 医者が取るか坊主が取るか(いしゃがとるかぼうずがとるか)
- 医者寒からず儒者寒し(いしゃさむからずじゅしゃさむし)
- 医者上手にかかり下手(いしゃじょうずにかかりべた)
「一」を含むことわざ
- 悪は一旦の事なり(あくはいったんのことなり)
- 欠伸を一緒にすれば三日従兄弟(あくびをいっしょにすればみっかいとこ)
- 朝顔の花一時(あさがおのはなひととき)
- 朝の一時は晩の二時に当たる(あさのひとときはばんのふたときにあたる)
- 薊の花も一盛り(あざみのはなもひとさかり)
- あの世の千日、この世の一日(あのよのせんにち、このよのいちにち)
- 危ない橋も一度は渡れ(あぶないはしもいちどはわたれ)
- 粟一粒は汗一粒(あわひとつぶはあせひとつぶ)
- 板子一枚下は地獄(いたごいちまいしたはじごく)
- 一瓜実に二丸顔(いちうりざねににまるがお)
「時」を含むことわざ
- 挨拶は時の氏神(あいさつはときのうじがみ)
- 朝顔の花一時(あさがおのはなひととき)
- 朝の一時は晩の二時に当たる(あさのひとときはばんのふたときにあたる)
- あの声で蜥蜴食らうか時鳥(あのこえでとかげくらうかほととぎす)
- ある時は米の飯(あるときはこめのめし)
- ある時払いの催促なし(あるときばらいのさいそくなし)
- いざという時(いざというとき)
- 何時にない(いつにない)
- 今を時めく(いまをときめく)
- 飢えたる時は食を択ばず(うえたるときはしょくをえらばず)



