立てば芍薬、座れば牡丹、歩く姿は百合の花とは
立てば芍薬、座れば牡丹、歩く姿は百合の花
たてばしゃくやく、すわればぼたん、あるくすがたはゆりのはな
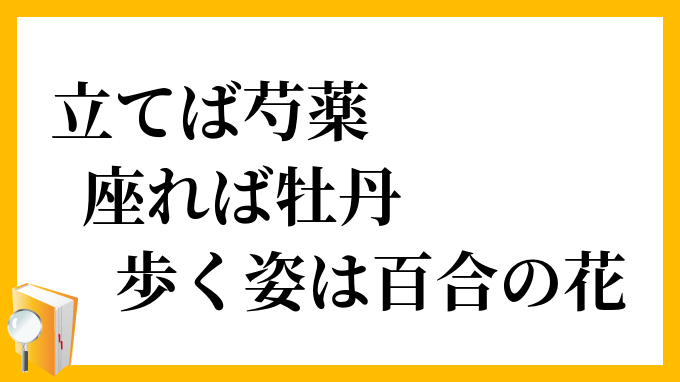
| 言葉 | 立てば芍薬、座れば牡丹、歩く姿は百合の花 |
|---|---|
| 読み方 | たてばしゃくやく、すわればぼたん、あるくすがたはゆりのはな |
| 意味 | 美人の容姿や立ち居振る舞いを形容することば。 |
| 場面用途 | 美人・美女 |
| 類句 | 立てば芍薬、座れば牡丹 |
| 使用語彙 | 芍薬 / 牡丹 / 歩く / 姿 / 百合 / 花 |
| 使用漢字 | 立 / 芍 / 薬 / 座 / 牡 / 丹 / 歩 / 姿 / 百 / 合 / 花 |
「立」を含むことわざ
- 愛立てないは祖母育ち(あいだてないはばばそだち)
- 間に立つ(あいだにたつ)
- 青筋を立てる(あおすじをたてる)
- 証を立てる(あかしをたてる)
- 秋風が立つ(あきかぜがたつ)
- 商人と屏風は直ぐには立たぬ(あきんどとびょうぶはすぐにはたたぬ)
- 足下から鳥が立つ(あしもとからとりがたつ)
- 頭から湯気を立てる(あたまからゆげをたてる)
- あちら立てればこちらが立たぬ(あちらたてればこちらがたたぬ)
- 石に立つ矢(いしにたつや)
「芍」を含むことわざ
- 立てば芍薬、座れば牡丹、歩く姿は百合の花(たてばしゃくやく、すわればぼたん、あるくすがたはゆりのはな)
- 立てば芍薬、座れば牡丹(たてばしゃくやくすわればぼたん)
「薬」を含むことわざ
- 青葉は目の薬(あおばはめのくすり)
- 姉女房は身代の薬(あねにょうぼうはしんだいのくすり)
- いい薬になる(いいくすりになる)
- 医者の薬も匙加減(いしゃのくすりもさじかげん)
- 一に看病、二に薬(いちにかんびょう、ににくすり)
- 生まれたあとの早め薬(うまれたあとのはやめぐすり)
- 大きい薬缶は沸きが遅い(おおきいやかんはわきがおそい)
- 薬師は人を殺せど薬人を殺さず(くすしはひとをころせどくすりひとをころさず)
- 薬が効く(くすりがきく)
- 薬になる(くすりになる)
「座」を含むことわざ
- 胡座で川(あぐらでかわ)
- 胡座をかく(あぐらをかく)
- 後釜に座る(あとがまにすわる)
- お座敷が掛かる(おざしきがかかる)
- 器量は当座の花(きりょうはとうざのはな)
- 後光より台座が高くつく(ごこうよりだいざがたかくつく)
- 座が白ける(ざがしらける)
- 座がもたない(ざがもたない)
- 座禅組むより肥やし汲め(ざぜんくむよりこやしくめ)
- 座右の銘(ざゆうのめい)
「牡」を含むことわざ
- 開いた口へ牡丹餅(あいたくちへぼたもち)
- Rのない月の牡蠣はよくない(あーるのないつきのかきはよくない)
- 立てば芍薬、座れば牡丹(たてばしゃくやくすわればぼたん)
- 棚から牡丹餅(たなからぼたもち)
- 棚から牡丹餅は落ちてこない(たなからぼたもちはおちてこない)
- 牡丹に唐獅子、竹に虎(ぼたんにからじし、たけにとら)
- 夜食過ぎての牡丹餅(やしょくすぎてのぼたもち)
- 夢に牡丹餅(ゆめにぼたもち)
「丹」を含むことわざ
- 開いた口へ牡丹餅(あいたくちへぼたもち)
- 食後の一睡、万病丹(しょくごのいっすい、まんびょうたん)
- 臍下丹田に力を入れる(せいかたんでんにちからをいれる)
- 立てば芍薬、座れば牡丹(たてばしゃくやくすわればぼたん)
- 棚から牡丹餅(たなからぼたもち)
- 棚から牡丹餅は落ちてこない(たなからぼたもちはおちてこない)
- 丹精を込める(たんせいをこめる)
- 丹精を凝らす(たんせいをこらす)
- 丹精を尽くす(たんせいをつくす)
「歩」を含むことわざ
- 歩く足には塵が付く(あるくあしにはちりがつく)
- 一歩譲る(いっぽゆずる)
- 一歩を踏み出す(いっぽをふみだす)
- 犬も歩けば棒に当たる(いぬもあるけばぼうにあたる)
- 牛の歩み(うしのあゆみ)
- 蟹を縦に歩かせることはできない(かにをたてにあるかせることはできない)
- 邯鄲の歩み(かんたんのあゆみ)
- 五十歩百歩(ごじっぽひゃっぽ)
- 七歩の才(しちほのさい)
- 千里の道も一歩から(せんりのみちもいっぽから)
「姿」を含むことわざ
- 心につるる姿(こころにつるるすがた)
- 姿勢を正す(しせいをただす)
- 姿は俗性を現す(すがたはぞくしょうをあらわす)
- 姿は作り物(すがたはつくりもの)
- 立てば芍薬、座れば牡丹、歩く姿は百合の花(たてばしゃくやく、すわればぼたん、あるくすがたはゆりのはな)
「百」を含むことわざ
- 悪妻は百年の不作(あくさいはひゃくねんのふさく)
- 朝起き千両、夜起き百両(あさおきせんりょう、よおきひゃくりょう)
- 明日の百より今日の五十(あすのひゃくよりきょうのごじゅう)
- 一日一字を学べば三百六十字(いちにちいちじをまなべばさんびゃくろくじゅうじ)
- 一文惜しみの百知らず(いちもんおしみのひゃくしらず)
- 一犬影に吠ゆれば百犬声に吠ゆ(いっけんかげにほゆればひゃっけんこえにほゆ)
- 嘘八百(うそはっぴゃく)
- 江戸は八百八町、大坂は八百八橋(えどははっぴゃくやちょう、おおさかははっぴゃくやばし)
- 男は裸百貫(おとこははだかひゃっかん)
- お百度を踏む(おひゃくどをふむ)
「合」を含むことわざ
- 合言葉にする(あいことばにする)
- 合性が悪い(あいしょうがわるい)
- 合いの手を入れる(あいのてをいれる)
- 合間を縫う(あいまをぬう)
- 合うも不思議合わぬも不思議(あうもふしぎあわぬもふしぎ)
- 合わせ物は離れ物(あわせものははなれもの)
- 合わせる顔がない(あわせるかおがない)
- 合わぬ蓋あれば合う蓋あり(あわぬふたあればあうふたあり)
- 息が合う(いきがあう)
- 意気投合する(いきとうごうする)



