世の中は三日見ぬ間の桜かなとは
世の中は三日見ぬ間の桜かな
よのなかはみっかみぬまのさくらかな
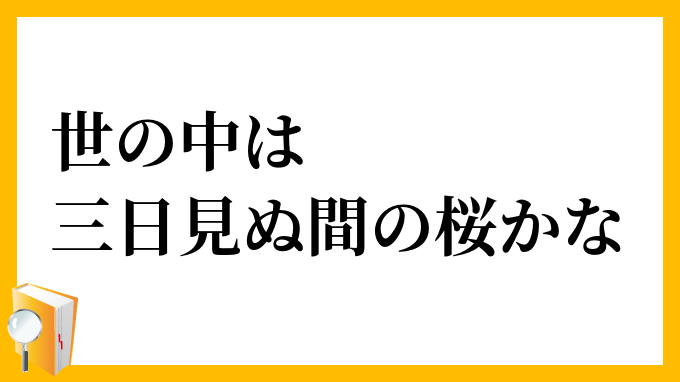
| 言葉 | 世の中は三日見ぬ間の桜かな |
|---|---|
| 読み方 | よのなかはみっかみぬまのさくらかな |
| 意味 | 桜の花があっという間に散ってしまうように、世間の移り変わりは激しいものだということ。
もとは江戸時代の俳人大島蓼太の句「世の中は三日見ぬ間に桜かな」から。 この句は「桜が散ってしまうこと」ではなく「桜が咲きそろうこと」を詠んだもの。 単に「三日見ぬ間の桜」ともいう。 |
| 異形 | 世の中は三日見ぬ間に桜かな(よのなかはみっかみぬまにさくらかな) |
| 三日見ぬ間の桜(みっかみぬまのさくら) | |
| 使用語彙 | 世の中 / 世 / 三日 / 桜 / かな |
| 使用漢字 | 世 / 中 / 三 / 日 / 見 / 間 / 桜 |
「世」を含むことわざ
- 明日知らぬ世(あすしらぬよ)
- あの世の千日、この世の一日(あのよのせんにち、このよのいちにち)
- 石の物言う世の中(いしのものいうよのなか)
- 一世を風靡する(いっせいをふうびする)
- いらぬお世話の蒲焼(いらぬおせわのかばやき)
- 有為転変は世の習い(ういてんぺんはよのならい)
- 浮世の風(うきよのかぜ)
- 浮世は衣装七分(うきよはいしょうしちぶ)
- 浮世は回り持ち(うきよはまわりもち)
- 浮世は夢(うきよはゆめ)
「中」を含むことわざ
- 麻の中の蓬(あさのなかのよもぎ)
- 中らずと雖も遠からず(あたらずといえどもとおからず)
- 当て事と越中褌は向こうから外れる(あてごととえっちゅうふんどしはむこうからはずれる)
- 後先息子に中娘(あとさきむすこになかむすめ)
- 石の物言う世の中(いしのものいうよのなか)
- 意中の人(いちゅうのひと)
- 井の中の蛙大海を知らず(いのなかのかわずたいかいをしらず)
- 魚の釜中に遊ぶが如し(うおのふちゅうにあそぶがごとし)
- 海中より盃中に溺死する者多し(かいちゅうよりはいちゅうにできしするものおおし)
- 渦中に巻き込まれる(かちゅうにまきこまれる)
「三」を含むことわざ
- 商い三年(あきないさんねん)
- 秋の雨が降れば猫の顔が三尺になる(あきのあめがふればねこのかおがさんじゃくになる)
- 顎振り三年(あごふりさんねん)
- 朝起きは三文の徳(あさおきはさんもんのとく)
- 雨垂れは三途の川(あまだれはさんずのかわ)
- 家を道端に作れば三年成らず(いえをみちばたにつくればさんねんならず)
- 石の上にも三年(いしのうえにもさんねん)
- 伊勢へ七度、熊野へ三度(いせへななたび、くまのへみたび)
- 居候、三杯目にはそっと出し(いそうろう、さんばいめにはそっとだし)
- 一押し、二金、三男(いちおし、にかね、さんおとこ)
「日」を含むことわざ
- 秋風と夫婦喧嘩は日が入りゃ止む(あきかぜとふうふげんかはひがいりゃやむ)
- 秋の入り日と年寄りはだんだん落ち目が早くなる(あきのいりひととしよりはだんだんおちめがはやくなる)
- 秋の日と娘の子はくれぬようでくれる(あきのひとむすめのこはくれぬようでくれる)
- 秋の日は釣瓶落とし(あきのひはつるべおとし)
- 秋日和半作(あきびよりはんさく)
- 明後日の方(あさってのほう)
- 朝日が西から出る(あさひがにしからでる)
- 明日は明日の風が吹く(あしたはあしたのかぜがふく)
- 明日ありと思う心の仇桜(あすありとおもうこころのあだざくら)
- 明日食う塩辛に今日から水を飲む(あすくうしおからにきょうからみずをのむ)
「見」を含むことわざ
- 相手見てからの喧嘩声(あいてみてからのけんかごえ)
- 青菜は男に見せな(あおなはおとこにみせな)
- 足元を見る(あしもとをみる)
- 後先見ず(あとさきみず)
- 穴の開くほど見る(あなのあくほどみる)
- 甘く見る(あまくみる)
- いい目を見る(いいめをみる)
- 戦を見て矢を矧ぐ(いくさをみてやをはぐ)
- 意見と餅はつくほど練れる(いけんともちはつくほどねれる)
- 何れを見ても山家育ち(いずれをみてもやまがそだち)
「間」を含むことわざ
- 間に立つ(あいだにたつ)
- 合間を縫う(あいまをぬう)
- あっという間(あっというま)
- 鼬なき間の貂誇り(いたちなきまのてんほこり)
- 鬼の居ぬ間に洗濯(おにのいぬまにせんたく)
- 間、髪を容れず(かん、はつをいれず)
- 間一髪(かんいっぱつ)
- 間隙を生じる(かんげきをしょうじる)
- 間隙を縫う(かんげきをぬう)
- 間然するところなし(かんぜんするところなし)



