腹八分に医者いらずとは
腹八分に医者いらず
はらはちぶにいしゃいらず
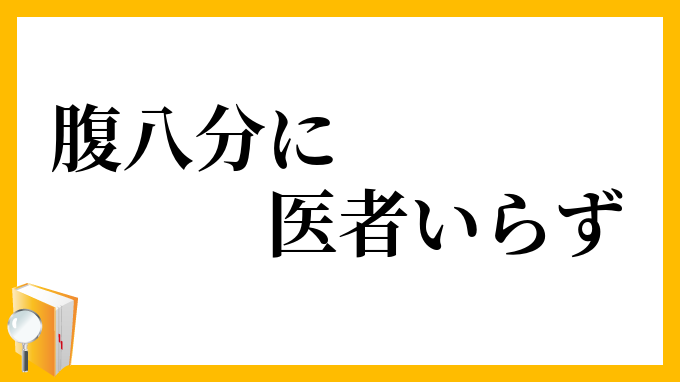
| 言葉 | 腹八分に医者いらず |
|---|---|
| 読み方 | はらはちぶにいしゃいらず |
| 意味 | 食事をするときは、常に満腹の八割ほどに抑えておくほうが健康でいられるということ。
「腹八分目に医者いらず」「腹八合に医者いらず」「腹八合に病なし」などともいう。 |
| 異形 | 腹八分目に医者いらず(はらはちぶんめにいしゃいらず) |
| 腹八合に医者いらず(はらはちごうにいしゃいらず) | |
| 腹八合に病なし(はらはちごうにやまいなし) | |
| 場面用途 | 食事 |
| 類句 | 腹も身のうち(はらもみのうち) |
| 大食は命の取り越し | |
| 使用語彙 | 腹八分 / 八分 / 八 / 医者 / 腹八分目 / 八分目 |
| 使用漢字 | 腹 / 八 / 分 / 医 / 者 / 目 / 合 / 病 |
「腹」を含むことわざ
- 後腹が病める(あとばらがやめる)
- 諍いをしいしい腹を大きくし(いさかいをしいしいはらをおおきくし)
- 痛くもない腹を探られる(いたくもないはらをさぐられる)
- 言わねば腹ふくる(いわねばはらふくる)
- 海魚腹から川魚背から(うみうおはらからかわうおせから)
- 思うこと言わねば腹ふくる(おもうこといわねばはらふくる)
- 恩の腹は切らねど情けの腹は切る(おんのはらはきらねどなさけのはらはきる)
- 片腹痛い(かたはらいたい)
- 聞けば聞き腹(きけばききばら)
- 魚腹に葬らる(ぎょふくにほうむらる)
「八」を含むことわざ
- 朝寝八石の損(あさねはちこくのそん)
- 当たるも八卦、当たらぬも八卦(あたるもはっけ、あたらぬもはっけ)
- 一か八か(いちかばちか)
- 嘘八百(うそはっぴゃく)
- 嘘八百を並べる(うそはっぴゃくをならべる)
- 江戸は八百八町、大坂は八百八橋(えどははっぴゃくやちょう、おおさかははっぴゃくやばし)
- 鬼も十八(おにもじゅうはち)
- 鬼も十八、番茶も出花(おにもじゅうはち、ばんちゃもでばな)
- 借りる八合、済す一升(かりるはちごう、なすいっしょう)
- 木七竹八塀十郎(きしちたけはちへいじゅうろう)
「分」を含むことわざ
- 預かり半分(あずかりはんぶん)
- 預かり半分の主(あずかりはんぶんのぬし)
- 預かり物は半分の主(あずかりものははんぶんのぬし)
- 預かる物は半分の主(あずかるものははんぶんのぬし)
- 一升徳利こけても三分(いっしょうどっくりこけてもさんぶ)
- 一寸の虫にも五分の魂(いっすんのむしにもごぶのたましい)
- 浮世は衣装七分(うきよはいしょうしちぶ)
- 馬の背を分ける(うまのせをわける)
- 鎹分別(かすがいふんべつ)
- 片口聞いて公事を分くるな(かたくちきいてくじをわくるな)
「医」を含むことわざ
- 医者が取るか坊主が取るか(いしゃがとるかぼうずがとるか)
- 医者寒からず儒者寒し(いしゃさむからずじゅしゃさむし)
- 医者上手にかかり下手(いしゃじょうずにかかりべた)
- 医者と味噌は古いほどよい(いしゃとみそはふるいほどよい)
- 医者の薬も匙加減(いしゃのくすりもさじかげん)
- 医者の自脈効き目なし(いしゃのじみゃくききめなし)
- 医者の只今(いしゃのただいま)
- 医者の不養生(いしゃのふようじょう)
- 医者よ自らを癒せ(いしゃよみずからをいやせ)
- 医は仁術(いはじんじゅつ)
「者」を含むことわざ
- 愛出ずる者は愛返り、福往く者は福来る(あいいずるものはあいかえり、ふくゆくものはふくきたる)
- 青表紙を叩いた者にはかなわぬ(あおびょうしをたたいたものにはかなわぬ)
- 赤子のうちは七国七里の者に似る(あかごのうちはななくにななさとのものににる)
- 垢で死んだ者はない(あかでしんだものはない)
- 当たった者のふの悪さ(あたったもののふのわるさ)
- 新たに沐する者は必ず冠を弾く(あらたにもくするものはかならずかんむりをはじく)
- 医者が取るか坊主が取るか(いしゃがとるかぼうずがとるか)
- 医者寒からず儒者寒し(いしゃさむからずじゅしゃさむし)
- 医者上手にかかり下手(いしゃじょうずにかかりべた)
- 医者と味噌は古いほどよい(いしゃとみそはふるいほどよい)
「目」を含むことわざ
- 青葉は目の薬(あおばはめのくすり)
- 秋の入り日と年寄りはだんだん落ち目が早くなる(あきのいりひととしよりはだんだんおちめがはやくなる)
- 商人の子は算盤の音で目を覚ます(あきんどのこはそろばんのおとでめをさます)
- 麻殻に目鼻をつけたよう(あさがらにめはなをつけたよう)
- 朝題目に夕念仏(あさだいもくにゆうねんぶつ)
- 朝題目に宵念仏(あさだいもくによいねんぶつ)
- 網の目に風たまらず(あみのめにかぜたまらず)
- 網の目に風たまる(あみのめにかぜたまる)
- 網の目を潜る(あみのめをくぐる)
- いい目が出る(いいめがでる)
「合」を含むことわざ
- 合言葉にする(あいことばにする)
- 合性が悪い(あいしょうがわるい)
- 合いの手を入れる(あいのてをいれる)
- 合間を縫う(あいまをぬう)
- 合うも不思議合わぬも不思議(あうもふしぎあわぬもふしぎ)
- 合わす顔がない(あわすかおがない)
- 合わせ物は離れ物(あわせものははなれもの)
- 合わせる顔がない(あわせるかおがない)
- 合わぬ蓋あれば合う蓋あり(あわぬふたあればあうふたあり)
- 息が合う(いきがあう)



