九死に一生を得るとは
九死に一生を得る
きゅうしにいっしょうをえる
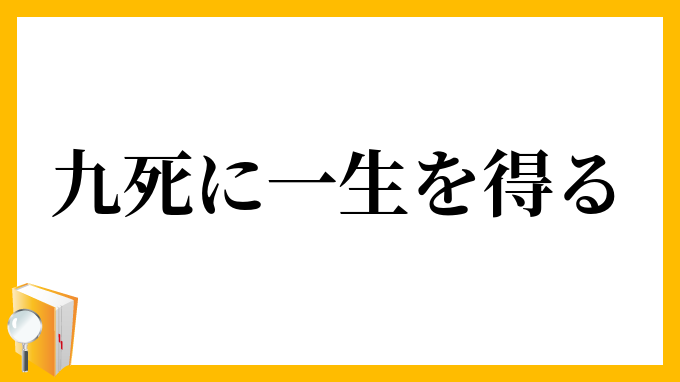
| 言葉 | 九死に一生を得る |
|---|---|
| 読み方 | きゅうしにいっしょうをえる |
| 意味 | ほとんど助かる見込みがないと思われる危険な状態に陥りながら、かろうじて助かること。
「十のうち、九が死、一が生」のような助かる見込みがほとんどない状況で生き残るとの意から。 「万死に一生を得る」「万死の中に一生を得」「万死を出でて一生に遇う」「九死一生」などともいう。 |
| 異形 | 万死に一生を得る(ばんしにいっしょうをえる) |
| 万死の中に一生を得(ばんしのうちにいっしょうをう) | |
| 万死を出でて一生に遇う(ばんしをいでていっしょうにあう) | |
| 使用語彙 | 九死 / 一生 / 得る |
| 使用漢字 | 九 / 死 / 一 / 生 / 得 / 万 / 中 / 出 / 遇 |
「九」を含むことわざ
- お前百までわしゃ九十九まで(おまえひゃくまでわしゃくじゅうくまで)
- 九牛の一毛(きゅうぎゅうのいちもう)
- 九仞の功を一簣に虧く(きゅうじんのこうをいっきにかく)
- 九尺二間に戸が一枚(くしゃくにけんにとがいちまい)
- 三十九じゃもの花じゃもの(さんじゅうくじゃものはなじゃもの)
- 三拝九拝する(さんぱいきゅうはいする)
- 葬礼九つ酒七つ(そうれいここのつさけななつ)
- 鶴九皐に鳴き、声天に聞こゆ(つるきゅうこうになき、こえてんにきこゆ)
- 天才とは一パーセントの霊感と九十九パーセントの汗である(てんさいとはいちぱーせんとのれいかんときゅうじゅうきゅうぱーせんとのあせである)
「死」を含むことわざ
- 垢で死んだ者はない(あかでしんだものはない)
- 朝に道を聞かば夕べに死すとも可なり(あしたにみちをきかばゆうべにしすともかなり)
- 慌てる蟹は穴の口で死ぬ(あわてるかにはあなのくちでしぬ)
- 生きている犬は死んだライオンに勝る(いきているいぬはしんだらいおんにまさる)
- 生き身は死に身(いきみはしにみ)
- 生きるべきか死すべきかそれが問題だ(いきるべきかしすべきかそれがもんだいだ)
- 一度死ねば二度死なぬ(いちどしねばにどしなぬ)
- 運を待つは死を待つに等し(うんをまつはしをまつにひとし)
- 親が死んでも食休み(おやがしんでもしょくやすみ)
- 泳ぎ上手は川で死ぬ(およぎじょうずはかわでしぬ)
「一」を含むことわざ
- 悪は一旦の事なり(あくはいったんのことなり)
- 欠伸を一緒にすれば三日従兄弟(あくびをいっしょにすればみっかいとこ)
- 朝顔の花一時(あさがおのはなひととき)
- 朝の一時は晩の二時に当たる(あさのひとときはばんのふたときにあたる)
- 薊の花も一盛り(あざみのはなもひとさかり)
- あの世の千日、この世の一日(あのよのせんにち、このよのいちにち)
- 危ない橋も一度は渡れ(あぶないはしもいちどはわたれ)
- 粟一粒は汗一粒(あわひとつぶはあせひとつぶ)
- 板子一枚下は地獄(いたごいちまいしたはじごく)
- 一瓜実に二丸顔(いちうりざねににまるがお)
「生」を含むことわざ
- 諦めは心の養生(あきらめはこころのようじょう)
- 徒花に実は生らぬ(あだばなにみはならぬ)
- 生き馬の目を抜く(いきうまのめをぬく)
- 生き肝を抜く(いきぎもをぬく)
- 生きた心地もしない(いきたここちもしない)
- 生きた空もない(いきたそらもない)
- 生き血を吸う(いきちをすう)
- 生きている犬は死んだライオンに勝る(いきているいぬはしんだらいおんにまさる)
- 生きとし生けるもの(いきとしいけるもの)
- 生き恥を曝す(いきはじをさらす)
「得」を含むことわざ
- 言い得て妙(いいえてみょう)
- 一文の得にもならない(いちもんのとくにもならない)
- 魚の水を得たよう(うおのみずをえたよう)
- 魚を得て筌を忘る(うおをえてうえをわする)
- 得体が知れない(えたいがしれない)
- 得たり賢し(えたりかしこし)
- 得手勝手は向こうには効かない(えてかってはむこうにはきかない)
- 得手に鼻つく(えてにはなつく)
- 得手に帆を揚げる(えてにほをあげる)
- 得も言われぬ(えもいわれぬ)
「万」を含むことわざ
- 一事が万事(いちじがばんじ)
- 一人虚を伝うれば万人実を伝う(いちにんきょをつたうればばんにんじつをつたう)
- 一将功成りて万骨枯る(いっしょうこうなりてばんこつかる)
- 一天万乗の君(いってんばんじょうのきみ)
- 一波纔かに動いて万波随う(いっぱわずかにうごいてまんぱしたがう)
- 一夫関に当たれば万夫も開くなし(いっぷかんにあたればばんぷもひらくなし)
- 家書万金に抵る(かしょばんきんにあたる)
- 風邪は万病のもと(かぜはまんびょうのもと)
- 食後の一睡、万病円(しょくごのいっすい、まんびょうえん)
- 食後の一睡、万病丹(しょくごのいっすい、まんびょうたん)
「中」を含むことわざ
- 顎で背中を搔く(あごでせなかをかく)
- 麻の中の蓬(あさのなかのよもぎ)
- 中らずと雖も遠からず(あたらずといえどもとおからず)
- 当て事と越中褌は向こうから外れる(あてごととえっちゅうふんどしはむこうからはずれる)
- 後先息子に中娘(あとさきむすこになかむすめ)
- 石の物言う世の中(いしのものいうよのなか)
- 意中の人(いちゅうのひと)
- 井の中の蛙大海を知らず(いのなかのかわずたいかいをしらず)
- 魚の釜中に遊ぶが如し(うおのふちゅうにあそぶがごとし)
- 海中より盃中に溺死する者多し(かいちゅうよりはいちゅうにできしするものおおし)
「出」を含むことわざ
- 愛出ずる者は愛返り、福往く者は福来る(あいいずるものはあいかえり、ふくゆくものはふくきたる)
- 愛は小出しにせよ(あいはこだしにせよ)
- 青は藍より出でて藍より青し(あおはあいよりいでてあいよりあおし)
- 垢は擦るほど出る、あらは探すほど出る(あかはこするほどでる、あらはさがすほどでる)
- 明るみに出る(あかるみにでる)
- 顎を出す(あごをだす)
- 朝日が西から出る(あさひがにしからでる)
- 足が出る(あしがでる)
- 足を出す(あしをだす)
- 仇も情けも我が身より出る(あだもなさけもわがみよりでる)
「遇」を含むことわざ
- 孔子も時に遇わず(こうしもときにあわず)
- 時に遇う(ときにあう)
- 時に遇えば鼠も虎になる(ときにあえばねずみもとらになる)
- 万死を出でて一生に遇う(ばんしをいでていっしょうにあう)



